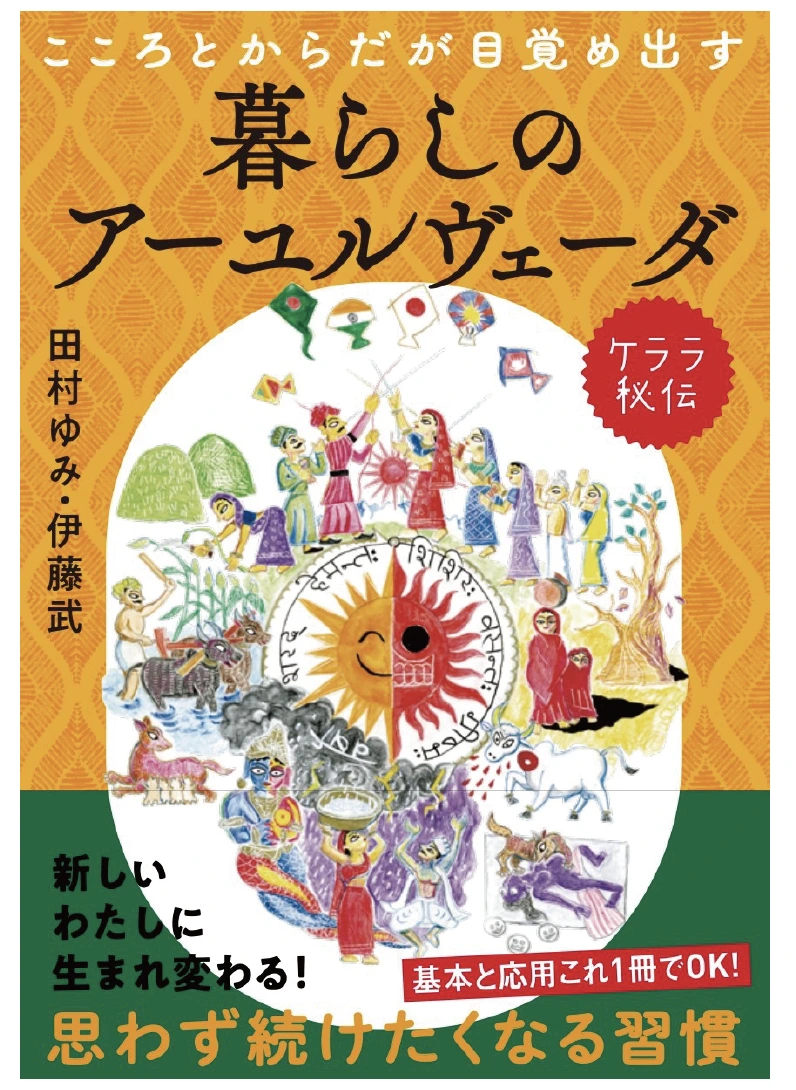
『ケララ秘伝
暮らしのアーユルヴェーダ』
伊藤武・田村ゆみ共著
Amazon
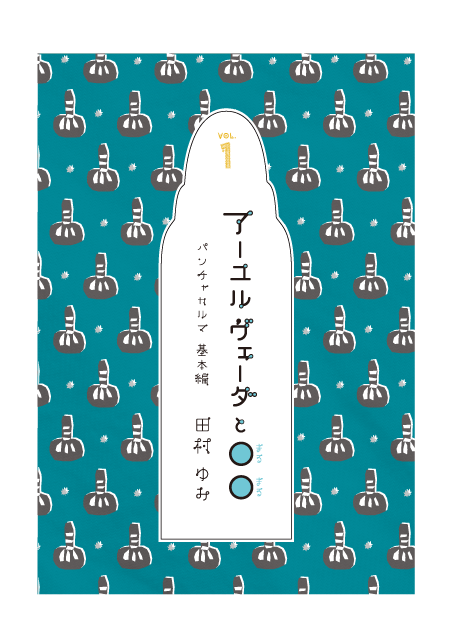
『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』田村ゆみ著
オンラインストア

6月のインドの歩き方で、とっても良いものをいただきました!
くださったのは、まちかど倶楽部のあきらジー。日本に南インドの古典音楽や伝統芸能を紹介、昨年は大ヒットした映画「響け!情熱のムリダンガム」に出演していた四人のミュージシャンを日本に招聘するなど、精力的に活動されています。
奈良のくすり文化が気になっていたAROUND INDIAに、なんてタイムリーなプレゼントでしょう。

薬湯って、すごく惹かれます。東大寺の薬湯となると、さらに効きそうな感じがしちゃいます。
東大寺の薬湯「天真」は、光明皇后1250年遠忌にちなみ、2010年に商品として開発されたものなのだそうですが、毎年3月に二月堂で行われる「修二会(お水取り)」の際にお坊さんたちが浸かるお風呂とほぼ同じものなんですって。
鎌倉の明王院では、「丁子(クローブ)の薬湯に浸かる」とおっしゃっていました。
こうなると全国のお寺の薬湯事情も気になってくる……。
ご存知の方がいらしたら、ぜひAROUND INDIAに教えてください。
正倉院の『種々薬草帳』に記載されている生薬からブレンド。
しかも全て地元で栽培されたものという、奈良と歴史がギュッと詰まった薬湯です。
日局トウキ・日局センキュウ・日局オウバク・日局ソウジュツ・日局サンシシ・日局チンピ・日局ジュウヤク・日局バンショウ

医薬部外品です。
冷え性、神経痛、腰痛、リウマチ、肩のこり、うちみ、くじき、しもやけ、ひび、あかぎれ、痔、あせも、疲労回復
開封すると、もう生薬の良い香り!
しかもパックはオレンジ色の模様が付いているのかと思ったら、濃い生薬成分がしみ出していたようです。

お風呂に入れるとすぐ、お湯が黄金色に染まりました。
使用法に書いてある通り“浸かりながら揉み出して”みると、さらに濃い色のお湯が楽しめ、香りも広がりました。
しばし目を閉じて、香りを楽しんだり、アーユルヴェーダのキリのように、肩や首にポンポンと当てました。夏は外は暑くても、冷房で冷えますからね。

いつもより温まりが早く、ぽかぽかが長続き。
薬湯って、入浴後も、ふとした時にほんのり香るのが好き。

染料にもつかわれるオウバク(黄柏・きはだ)やサンシシ(山梔子・くちなし)によるものだと思いますが、浴槽も染まっていました。
入浴後すぐに、普通の洗剤+漂白でさっと掃除したらきれいに取れました。
「色が出たらパックを引き上げると、1パックで3回くらい使える」そうなので、早めに引き上げるとお掃除は楽かもしれません。
でもせっかくの薬湯ですから、やっぱり濃くして入るのがおすすめです。
お求めは、東大寺オンラインショップでどうぞ。
https://todaiji.myshopify.com/products/%E8%96%AC%E6%B9%AF