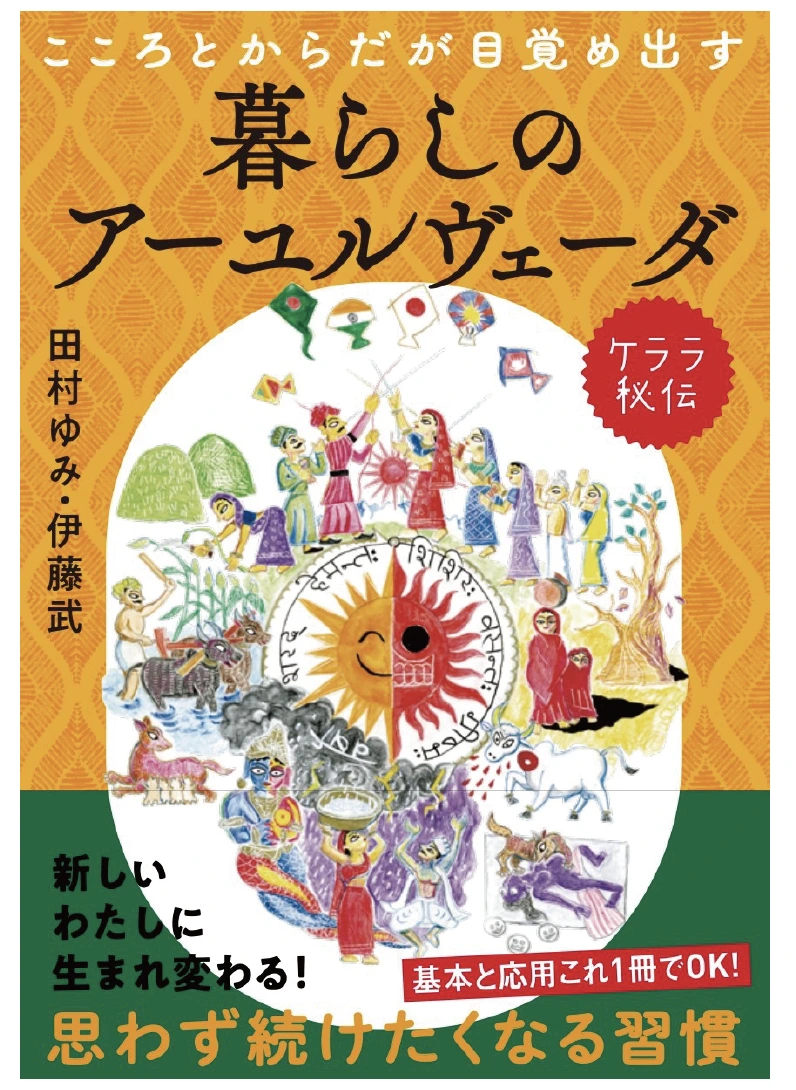
『ケララ秘伝
暮らしのアーユルヴェーダ』
伊藤武・田村ゆみ共著
Amazon
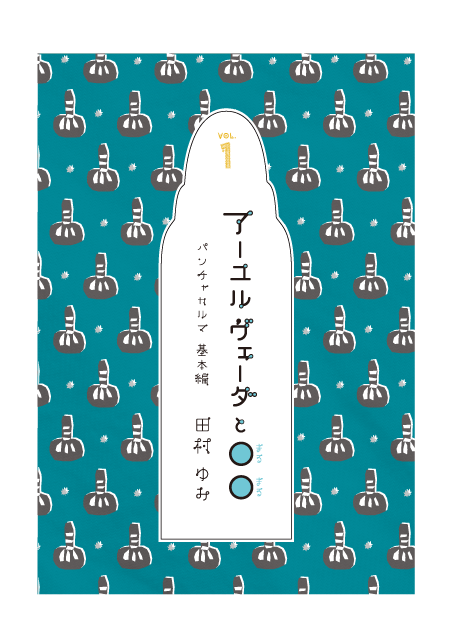
『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』田村ゆみ著
オンラインストア
AROUND INDIAがナチュロパシーという言葉を知ったのは、2008年、インドでアーユルヴェーダを学んでいたときのことでした。
学んでいた病院ではナチュロパシーも治療に取り入れていたため、上級クラスではナチュロパシーも教わりました。
理論と実技を通して、アーユルヴェーダとの違いも知ることができたのが、とてもよかったです。
実技では、じゃがいもで目元をパックをしたり、水を使ってマッサージをしたり、食事療法もあらたな理論で新鮮でした。
インド、特にケララでは、本物のアーユルヴェーダが身近にあり、気軽に診察・投薬・トリートメントを受けることができます。
でも、日本もそうであるように、アーユルヴェーダが身近ではない環境の方が一般的です。
どこでもできる五大元素を用いるトリートメントは、AROUND INDIAの暮らしのアーユルヴェーダにとって、重要なヒントになりました。



その後、インドのドクターに教わるオンラインコースも受講しました。
情報は盛りだくさんで勉強になりましたが、実技については当然説明だけなので、五感を使って覚えたいわたしみたいな人には、対面のクラスをおすすめします。
トリートメントが魅力的だった一方、授業で教わった食事療法には、まるで魅力を感じませんでした。
というのも、昼ごはん「蒸した野菜をひとつかみと……」
夜ごはん「蒸した野菜をひとつかみと……」
といった表現で、味つけもなく、健康に生きるためだけのごはんという響きだったからです。
しかも、ナチュロパシーでは断食を重視しているので、わたしの頭の中では、もう
「ナチュロパシーをするなら、一生おいしさとは さよなら」というイメージがでした。
ですが、ある日ドクターから「近くにナチュロパシーの食堂がある」と教わり、食べに行ってみました。
衝撃を受けました!
ナチュロパシー=おいしくなさそうというのは、完全にまちがいだったから
日本で自然系というと、若い女性が好みそうなイメージですが、ケララのナチュロパシー食堂は普通の食堂となんら変わらず、おじさん達がいっぱい。
白米ではなく赤米、ベジのみといったナチュロパシーらしい特徴がありつつも、特に真新しいものではなく、普通のケララ料理だったのです。
一気に、ナチュロパシーの料理=おいしいという認識に変わりました。
 ゆみ
ゆみ食べたことで、本当のナチュロパシーを学ぶことができました。
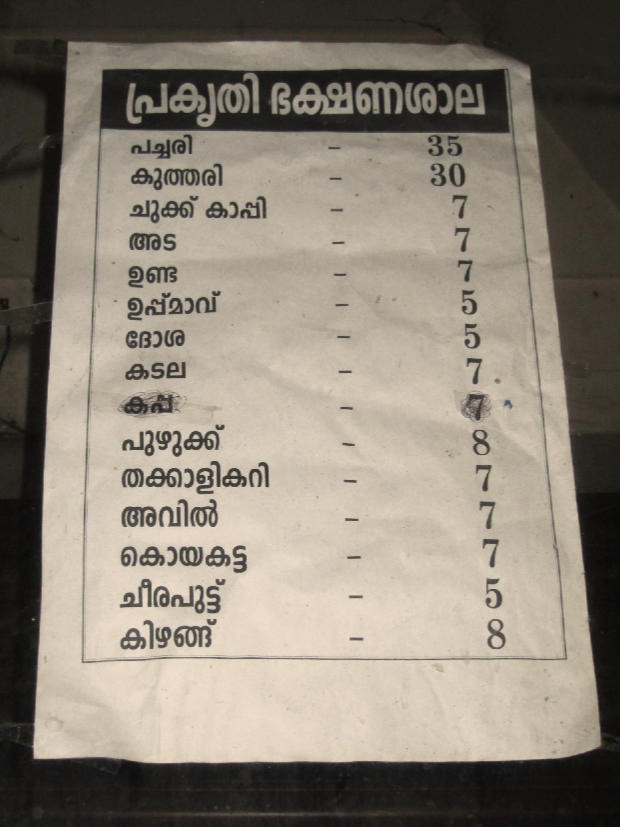
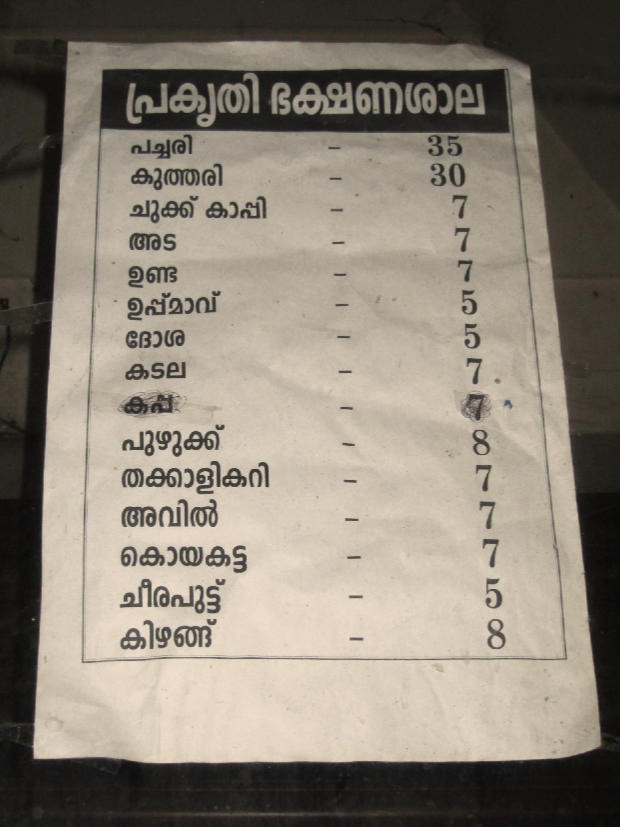




メニューは、パッチャリ、クッタリ、チュックカーッピ、アダ、ウンダ、ウップマーブ、ドーシャ、カダラ、カッパ、タッカーリカリー、アヴィル、チーラプットゥなどなど。
メニューについては、南インド・ケララ料理 用語集もどうぞ。


ケララ州都トリヴァンドラムで通ったのが、ナチュロパシードクターが運営するレストラン。
こちらは、通いたくなる!おいしいナチュロパシーレストラン「Pathayam」|ケララ州トリヴァンドラムをどうぞ。


ナチュロパシーには、ジュース療法、アルカリ食品療法など、さまざまな食事療法があります。