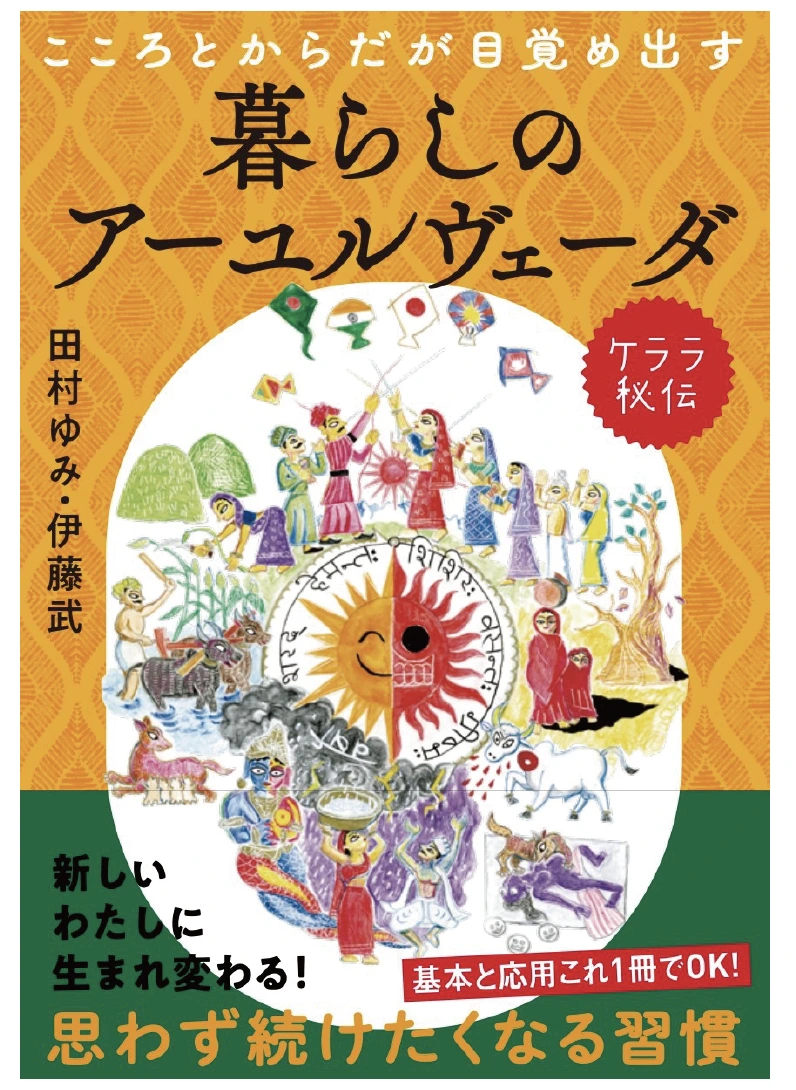
『ケララ秘伝
暮らしのアーユルヴェーダ』
伊藤武・田村ゆみ共著
Amazon
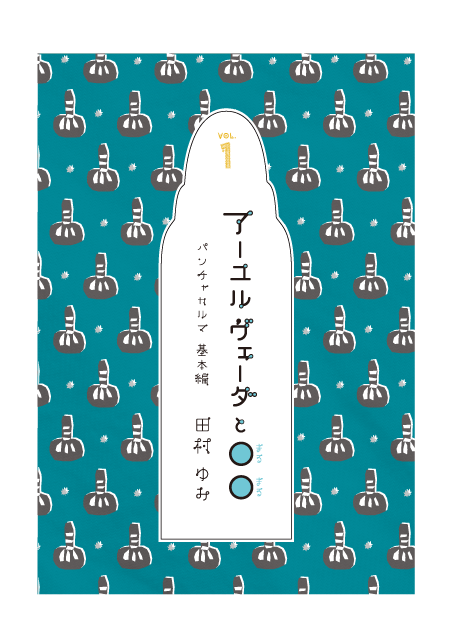
『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』田村ゆみ著
オンラインストア

島川あめ店の創業は、寛文三年(1663年)。江戸時代、徳川家綱将軍の時代というから驚きです。
あまりの歴史に、ほんの少し緊張しながら暖簾をくぐると、笑顔で「舐めてみて〜」と割り箸にからめた水あめをひとすくいくださいました。

いただいた飴は、とってもやさしい味で、じんわり甘さがやってきます。
その甘さはけっしてしつこくなく、すぅっと馴染んで消えていくのです。

島川あめ店の資料をもとに手順をご紹介しますと、
昔ながらの製法で、澱粉と麦芽のみを炊き上げてつくられたあめは、富山のくすり文化には欠かせない存在でした。
あるときは薬の苦味を抑え、あるときは丸薬にまとめるために。
「神薬」というかわいらしい青色のガラス瓶に入っていたというお薬は(名前からして効きそう!)、あめに着付け薬などの成分が入れられていたのだそう。

戦争になると、統制により甘いものが禁止されてしまいますが、島川のあめはお薬として生き残ることができたのだそうです。
しかしながら当時貴重となったお米は、あめの原料にすることはできなくなってしまったんですって。

大正時代の富山には7軒記録されているあめ店も、いまは島川あめ店を残すのみとなりました。
でも、こちらは最強だと思います。
だってもう、とにかく明るく笑顔がいっぱい。富山が好き!あめが好き!!というのが、奥さまとパート歴20年のスタッフさんから伝わってくるのです。

350周年記念で作られた冊子にも、温かい空気が詰まっていました。
「飴には人柄が出る」「仕事というよりも、たのしみである」
どのように向き合っていらっしゃるかがひしひしと伝わってきます。

富山のくすりには、立山信仰(山岳信仰)の修験者たちが各地の信者にお薬を配っていたという起源があるなど、翌日からの「富山のくすり」の勉強に先駆けて、実際にその一端を担ってきた方々からお話を聞くことができて、とても勉強になりました。
富山のくすり文化を支えてきた“あめ”。古に想いを馳せながら味わっていきたいですね。
