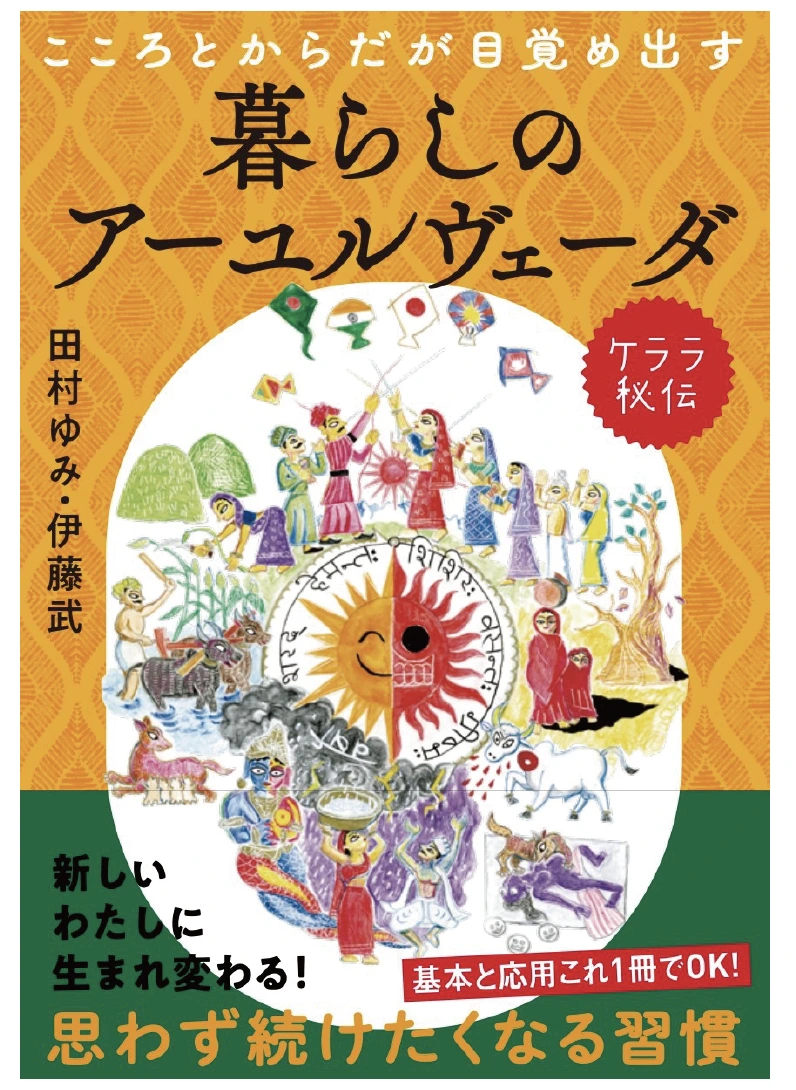
『ケララ秘伝
暮らしのアーユルヴェーダ』
伊藤武・田村ゆみ共著
Amazon
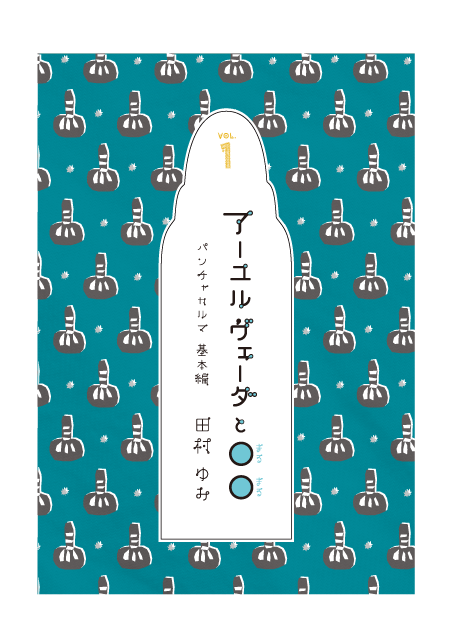
『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』田村ゆみ著
オンラインストア

昨年から、日本の伝統医学のことも少しずつ学んでいます。
まずは、日本薬科大学の山路教授の生薬の講義。漢方の全体像や歴史、生薬のことや煎じ薬の作り方、そして「診てもらうだけで治る」と言われるほどの漢方の大家の存在を教わりました。
続いては、北京出身の中医師であり漢方教育の普及に取り組んでこられた北陸大学の劉教授の中医学の講義。中国と日本で治療にあたってこられたご経験や、先生ご自身の活用法から、漢方薬の取り入れ方や、現在の日本で保険診療として受けられる漢方治療の範囲の広さや、エキス剤でも十分に良い結果が出ているということ。
さらに、富山大学の薬剤部長 加藤教授、東北大学の紺野研究員の漢方の講義を受け、ついに漢方のかかりつけ医を見つけることができました。
その後、鍼灸の講義を受け、大分医学技術専門学校の杉若先生のご紹介で鍼灸のかかりつけ医も見つけることができました。
これで、日本でも内科/外科の両側面がカバーされて心強いです。
(インドの場合、内科ならアーユルヴェーダ医や伝統医、外科ならカラリパヤットゥ師匠でした)
当初の学ぶ目的は「かかりつけ医を見つけること」ではなかったものの、「わたしなりのアーユルヴェーダとのバランスのいい付き合いかたが見つかった!!」気がしました。
アーユルヴェーダと出会えていなかったら、きっと今も生理痛を市販の強い鎮痛剤でごまかし、体温も低く、風邪をひきやすかったと思います。
医療としてのアーユルヴェーダを求めるならば、わたしはインドに受けに行きたいし、みなさんにも行って欲しいと思います。さまざまな患者さんを診つづけてきた医師が、あなたがどんな人で、これまでどんな不調を経験し、どんな対処をしてきたのか?そして今はどこに不調を感じているか、両親・祖父母は病気を経験したのかなどを総合的に診断し、粉や煎じ薬、薬酒、丸薬などの飲み薬、オイル、軟膏、ハーブペーストなどの塗り薬、パンチャカルマ浄化療法などを処方するからです。
日本では今のところアーユルヴェーダ薬は利用できないですし、トリートメントにも限りがあります。
かと言って、ほんとうに辛いときにインドに行くことや、薬の郵送もむずかしい。金銭的にも負担が大きくなります。
インドのアーユルヴェーダ病院やカラリの診療所にくる患者さんは、西洋医学の検査結果を持参したり、指示を受けて外部に検査を受けに行くこともあります。
昔、友人のアーユルヴェーダ医に「アーユルヴェーダにも注射はあるの?」と尋ねたら、
「針がこーんなに太いの。絶対イヤ!!注射は、絶対に西洋医学がいい」と言っていました。
現地では、骨折は伝統医がベストとか、ガンには西洋医学、よくわからないときはアーユルヴェーダ、体の痛みにはカラリなど、いろいろな選択肢があり柔軟に利用されていました。
アーユルヴェーダは、スリランカ、チベット、インドネシアなどで元々あった伝統医療と混ざり合い、土地に合う形に変化していきました。
日本の場合、元々の伝統医療は「漢方」ですね。でもわたしにとって漢方は、薬局、ドラッグストア、オンラインショップなどで目にはするものの、どう選べば良いのかわからない、近くて遠い存在でした。
たとえばドラッグストアにずらりと並んだ漢方薬。「生理」だけとっても、
「のぼせて足が冷える方の生理痛、生理に伴うイライラに」
「足腰の冷え、貧血や生理不順の方に」
「便秘がちな方の生理痛、生理時の精神不安に」
の3つがあり、選び方に困ります。
生理痛で悩んでいた頃の私は、イライラ、貧血、生理不順の三つが当てはまりました。
そうなるとどれを買うべきかわからないので、漢方は諦めていつもの鎮痛剤にしていたと思います。
ある程度の知識がないと選べないのです。
2002年より、医師になるためのカリキュラムに漢方が含まれているため、今では約9割の医師が漢方薬を処方した経験があるそうです。
よかったよかった!と思ってしまいそうですが、90分x8コマの劉教授の講義を受けたとき、医師のカリキュラムよりもたくさんの知識が詰まっているとおっしゃっていました。
カリキュラムに含まれる情報は限定されていて、それ以上の知識を増やすためには、ただでさえ忙しい医師になるための勉強に追加して、自主的に漢方を学ばないといけないのだそうです。
自主的に学ばれた医師が「漢方専門医」に認定されています。
漢方のかかりつけ医を見つける上で、わたしが重視したのは「処方してくれる医師」ではなく、「自分に合ったお薬を、その都度処方してくれる医師」。
漢方にもアーユルヴェーダにも副作用はあるので、自分で選んで、同じものを摂りつづけるといったことは危険をはらんでいます。
わたしは、漢方の受講を重ねるうちに、体質のことや、どのような薬が合うかなど、ほんの少し見えてきた気になりました。
いざ漢方専門医の診察を受けてみたら、まるで診たて違いでした。
ほんの少しでも見えた気になったのが恥ずかしい。笑
劉教授も「間違った漢方薬を自分で選んで、飲み続けているひとが多い」と仰っていました。
間違った自己診断は、不要な作用や、過剰な作用を得ることになってしまうわけです。イヤですね。
しかも漢方は変化に合わせて、2週間程度で処方を見直す必要があるとのこと。
お医者さんに、きちんと頼りましょう。
漢方は高いイメージがあるかもしれませんが、保険適用範囲も広く、わたしは診察もお薬も保険が使えて助かっています。
大きな病気になる前に不調をケアすることは、結局、医療費を抑えることにつながります。
湯に溶いて飲む顆粒の漢方煎じ薬(エキス剤)が主流ですが、千葉大学と富山大学は刻みの生薬も保険適用なんですって。
漢方薬もアーユルヴェーダも、植物・鉱物・動物が原料に使われています。
ほんの少量で強く効くものもあり、量や組み合わせには注意が必要です。
そこで気にしたいのが、ポリファーマシー問題。
生理痛用に〇〇、頭痛に▪️▪️、腰痛には△△のように、複数の漢方薬を飲んでいませんか?
眼科、整形外科、内科など、複数の診療科から、それぞれ処方を受けていませんか?
そうすると、重複する成分が過剰摂取になったり、副作用が起こりやすくなるなどの問題が生じる可能性があります。
かかりつけ医がいれば、西洋医学で受けた処方、服用している/していた漢方薬についても相談して、薬の飲みすぎを防ぐことができます。
もし、処方されていた薬が10種類→ 2種類に減ったとしたら、自己負担額が減る。国の負担も減る。
そして、心にも体にもやさしく、安心安全です。
それではいよいよ「漢方専門医の見つけかた」実践編です。
漢方にも流派があって、どの時代の中医学に基づいているかなどが変わってきます。
わたしは「千葉古方派」と呼ばれる和漢診療に興味をもちました。必要に応じて西洋医学も取り入れる漢方で、山路教授曰く、千葉メディカルセンターの寺澤先生は「この先生に見てもらうだけで病気が治る」と言われるほど名医なのだそうです。
寺澤先生のことがかなり気になり、ご著書を5冊読みました。
そして気づきました!
「寺澤先生の和漢診療学は、こんなのがあったらいいなぁと思い描いていた形だ」と。
寺澤先生の病院は通うには遠く、紹介状が必要なため、通える範囲で寺澤先生のお弟子さんを探すことにしました。
まず漢方専門医を探しました。
日本東洋医学会の専門医検索を利用すると便利です。西洋医学の分野からも検索できます。
わたしは、通える範囲の病院のホームページをひとつひとつ確認して、先生のご経歴をみて、寺澤先生のお弟子さんを見つけました。
その後、加藤教授より「(寺澤先生のお弟子さんにあたる先生方の病院一覧は)富山大学のホームページで調べることができる」と教わりました。
こちらのリストには全ての先生を網羅してはいないそうなので、先述の日本東洋医学会のデータベースと合わせて確認するのがオススメ。
こうして、寺澤先生の教え子にかかりつけ医になっていただくことができ、アーユルヴェーダと漢方のハイブリッドな暮らしがはじまりました。伝統医学たのしいなぁ。
もちろん、みなさんは、寺澤先生のお弟子さんにこだわる必要はありません。
良い先生はたくさんいらっしゃるし、いろんな流派・考え方があるから。
日本東洋医学会の専門医検索で、地域や専門で絞り、その先生のご経歴を確認して、ご本人や同じ流れを組む先生が執筆された書籍を読むと、お考えがわかると思います。
自分が「この先生いいな」と感じたところに行ってみてください。これから、いろいろと相談することになる先生だから。
みなさんも相性の良い漢方専門医と出会えますように。
加藤教授のお話に「いい患者さんになることについて」というものがありました。
いい患者さんとは、変化に気づいて伝えられる人。
かかりつけ医を見つけたら、いつどんな変化があったのか、どこがどんな風に辛いのか、先生に伝えましょう。
このことは、アーユルヴェーダの患者の役割とも共通します。
日常的に自分を観察して、記憶しておきましょう。