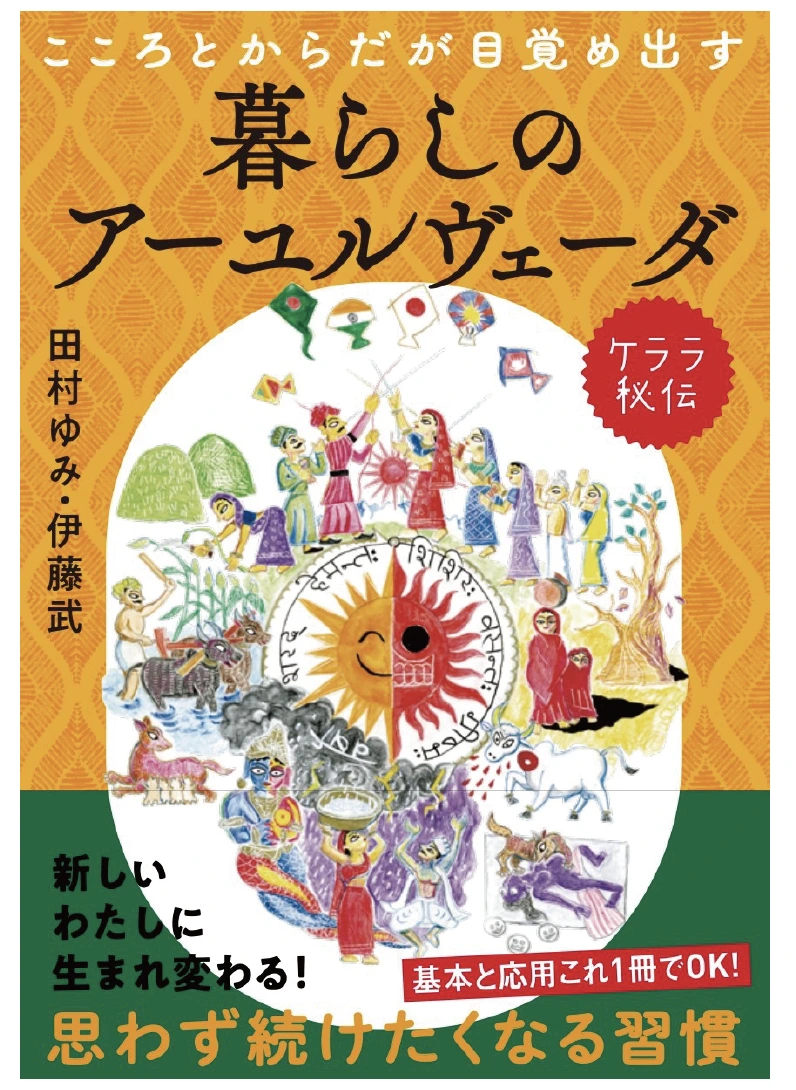
『ケララ秘伝
暮らしのアーユルヴェーダ』
伊藤武・田村ゆみ共著
Amazon
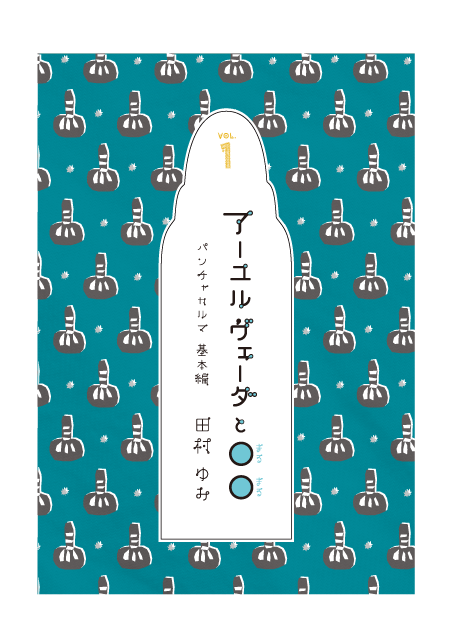
『アーユルヴェーダと〇〇 vol.1 パンチャカルマ基本編』田村ゆみ著
オンラインストア

アーユルヴェーダを学びにインドに行ったら、スーパーマーケットではペーストもたくさん売っていましたが、病院や薬局製の歯磨きはどこも粉でした。
わたしが初めに使ったのは、地元のアーユルヴェーダ製薬会社Asoka Pharmaceutical製のもの。
こちらで製造・販売していた歯磨き粉はこの一種類のみ。
開けたら真っ黒でビックリしました。
それ以来、いろんなアーユルヴェーダのものを使っていますが、結局この歯磨き粉を一番使っています。
味、歯磨き後の感覚、歯が白くなる感じが好きです。
主成分:クローブ、ナツメグ、生姜、黒胡椒
有用性:歯の変色を防ぐ、歯ぐきの健康を保ち、出血を予防する
インドのアーユルヴェーダドクターが我が家に滞在なさったときも粉の歯磨きを使用していて、わたしの家族が「本当に粉を使ってるんだね!」と驚いていました。
カラリの師匠は、お庭に生えているマンゴーの葉などが入った自家製で茶色。

ナチュロパシーを実践するシヴァナンダさんのお母さまは、育てている稲の籾殻を炭にしたもの。黒色。


息子のシヴァナンダさんは、かかりつけのナチュロパシー&アーユルヴェーダ病院からおすすめされたものを愛用。こちらは茶色。
原料:カレーリーフ、甘草、長胡椒、岩塩、クローブ、ナツメグ、黒胡椒など

アーンドラプラデーシュ州の伝統医のオリジナルは、歯磨きだけでなく、うがいや、ドライマッサージ用のパウダーとしても使える珍しい一品。
原料:メンソール、トゥルシ、ニームの炭、岩塩、ユーカリの葉、菖蒲など

期待したものの、意外に苦手だったのがKottakalというケララのアーユルヴェーダで一番の老舗のもの。
原料:アリメダ樹皮、甘草、インドメギ、アセンヤクノキ、カオリン(鉱物)、黒胡椒、長胡椒(ピッパリー)、メース、ナツメグ、ヒッチョウカ(クベバ)、クローブ、カルダモン、シナモン、樟脳、センティフォリアローズ
有用性:Arimedaがカパドーシャのバランスを整え、腫れや炎症を鎮め、健康な歯と息をサポートします。口臭、歯槽膿漏、虫歯に。
そして、こちらがケララのお隣タミルナドゥ州のもの。
完全にパケ買いでしたが、マドゥライ発祥の人気商品で、シッダ医学の知恵がベースになっています。
ピンクがかった紫色。

原料:イエローフルーツナイトシェード、クローブ、炭酸カルシウム、ミロバラン、シナモン、サッカリン、アマランス(着色料)

ある有名な歯磨き粉には「原料には書いてないけれど、研磨剤が入っている」と言われています。
多分そういう理由もあって、自家製を続けるひとが多いのかなって思います。
インドではじめて粉歯磨きを使ったころ、
『そういえば日本語でも、歯磨き「ペースト」じゃなくて「粉」って呼ぶなぁ。日本も昔は粉だったのかなぁ?』と想像していました。
実際それは大正解。
江戸初期(1643年)に、 丁字屋喜佐衛門という商人が朝鮮人に教えて貰ったのが歯みがき粉の始まり
神奈川県⻭科医師会 https://www.dent-kng.or.jp/museum/ja/hanohaku12/
神奈川県⻭科医師会によると、歯磨き粉は江戸時代からで、それより前は「焼き塩」や「焼き糠」を使っていたとのこと。
「焼き塩」や「焼き糠」は歯磨き粉とは呼ばないのですね。調合して、用途を絞ったものを「歯磨き粉」と呼ぶのかな?
日本の民間療法では「ナスの黒焼き」も有名。
江戸時代の歯磨き粉は、“房総半島で採れた房州砂(粘土の細かい粒子)に龍脳、丁字、桂心などの薬効成分を加えたもの”とのこと。
インドのアーユルヴェーダの歯磨き粉(現代でも使用されているもの)と、成分が近い!
インドでアーユルヴェーダを学ぶ楽しさって、こういうところにもあります。
日本で使っているもののルーツを知ることができて、さらに自分好みにアレンジして作ることもできるようになるから。
自著『ケララ秘伝 暮らしのアーユルヴェーダ』では、「第2章 春」の項目でニームという苦いアーユルヴェーダハーブを使った歯磨き粉レシピをご紹介しています。
リトリートで購入できるものもあるので、ご興味ある方は現地でご紹介するので言ってくださいね。
